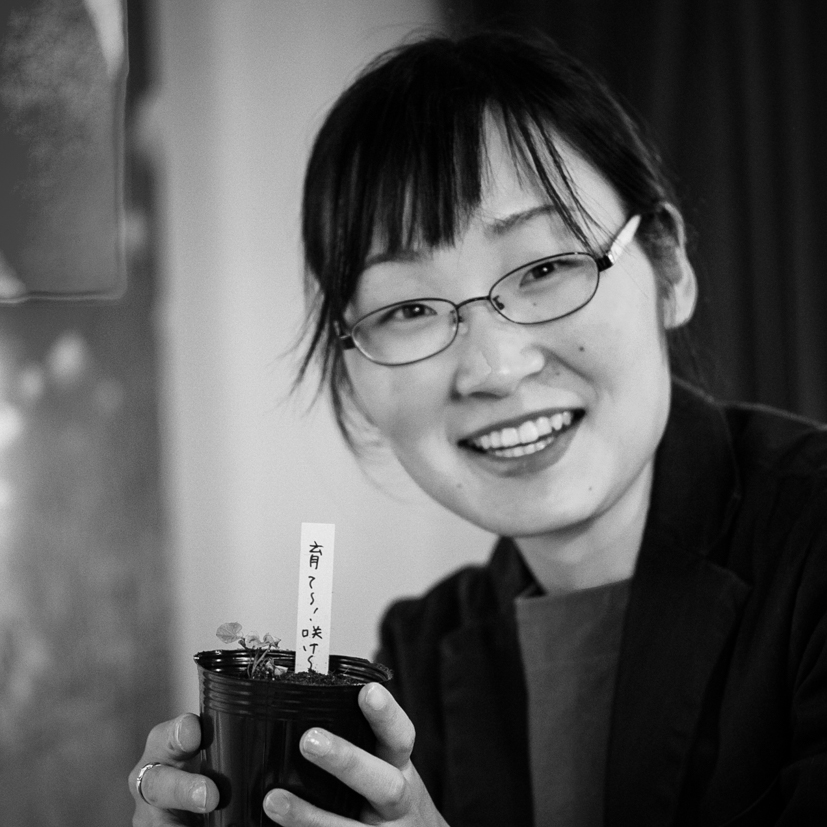3.11の書架 004 『春を恨んだりはしないー震災をめぐって考えたこと』

『春を恨んだりはしないー震災をめぐって考えたこと』(池澤夏樹著、2011年、中央公論新社)
所感
年が明けて、瞬く間に1月が終わり、短い2月に入る。
日々生活をこなしていると、ああ、もうすぐ3月が来るなと、半ばドキドキする。震災の記憶が思い出されるからだ。
3.11の記憶はその渦中にいなくても鮮明すぎて、生涯忘れることはないだろう。
北海道では、気温が上がり始め、日が暮れる時間も遅くなり、まだまだ寒いものの、「春」を意識させられる季節だ。
3.11の記憶がより一層くっきりする季節、でも決して「春を恨む」こともまたないだろう、と思う。
先日、とある本の中で池澤夏樹さんのインタビューを拝見して、その中でこの本の存在を知った。
何て詩的で美しいタイトルなんだろうと思い手に取った。
書名となっているこのフレーズはポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩からとったそうだ。
*
三月十一日以来、いろいろなことを考えている。あまりに多くの考えが湧いてきて収拾がつかなくなっている。
池澤さんは作家としてだろうか、言葉の持つ能力について考えていたのだと思う。
実際に、別の本の中で
追悼と慰霊については文学はまだ力があるんです。でも、未来に向けては、いま必要なのは論理の力、それから一人ひとりの聞き取る力であって、まだ文学の手には負えない気がする。
と書かれていた。
*
何かを考えることは言葉を伴うことで、言葉を使うことは言葉を向ける相手がいるということ。
ホモ・サピエンスの時代に、既に言葉は共に暮らす仲間との意思疎通・情報交換のためのもので、最初から会話の形をしていた。
だけれどもいつしか相手がいなくても架空の、抽象的な会話は展開できるようになり、それが信仰や哲学となった。
*
自然は人間に対して無関心だ。
自然にはいかなる意思もない。
自然は時に不幸を配布する。
重ねて自然のむごさの著述が出てくる。
なぜ地震や津波が人間を「襲った」というのか。
人間がその真実に耐えられず、ワンクッション持たせるために人間は自然に意思を持たせたのだと池澤さんは考えている。
*
日本にはそもそも昔から災害が多い。
本書であげられるのは、平安時代にやはり現在の東北地方で観測された貞観の大津波や、江戸時代に現在の長崎のあたりで起きた雲仙普賢岳の火山性地震・山体崩壊・津波である。
災害と復興がこの国の歴史の主軸ではなかったか。
2010年に日本の気象庁が震源を確定した地震は12万個を上回った。しかし、隣の韓国ではせいぜい年間40個程度である。
災害が我々の国民性を作った。
災害がわたしたち日本人の文化を形成していると考えると、不思議なポジティブささえ感じられる。
話は宗教にもおよび、中東のイスラム教、絶対神の存在は「不変」を意味するが、アジアの仏教、「無常」という原理は災害があるからこそ、日本に合った思想だというのにも合点がいってしまう。
著者は西欧のように議論を経て意図的に社会を構築することの少ない日本を憂いていたけど、日本人の「諦め」のよさ、「忘れる」ということは、大事なことだと考えるようになったという。
なぜならば、地震と津波には責任の問いようがないから。
*
原発に対する考えも出てくる。
世の事業の大半はこんな風に安全性を強調はしない。新幹線も飛行機も今さら『安全です』とは言わない。何かを隠そうとすればするほどそれが露わになる。形容詞の煉瓦を積めば積むほど、その後ろに何か見せたくないモノがあるとわかってしまう。
確かにそうだなと思ってしまう。
池澤さんは学生時代、大学で物理を勉強されていたのだそうだ。
科学では真理の探究が優先するが、工学には最初から目的がある。
原爆は科学ではなく工学の産物である。
として、目的優先の原爆への疑問を述べている。
限りなく成長する経済は健康にはほど遠い。それは癌と同じこと。
とアメリカの詩人、ゲイリー・スナイダーの言葉を引用している。
*
大部分は発災後から半年ほど現地で見聞きしたことから構成されるこの本だけれども、9年経つ今でも新鮮な考えや再認識させられる知識が詰まっている。
*
震災と津波はただただ無差別の受難でしかない。その負担をいかに広く薄く公平に分配するか、それを実行するのが生き残った者の責務である。
ダンスを踊ってはいけないのではない。東北の人々と共に踊る日のためにできることのすべてをした上で、その日を待ちながら、一人ででも踊る。
どうも9年経っても現状が変わらないような気がしてしまう。
でも、上記の言葉は震災のことだけに当てはまる言葉でもない。
生き残ったもの、生活に精神的・金銭的・物理的余力のあるものの使命を思う。