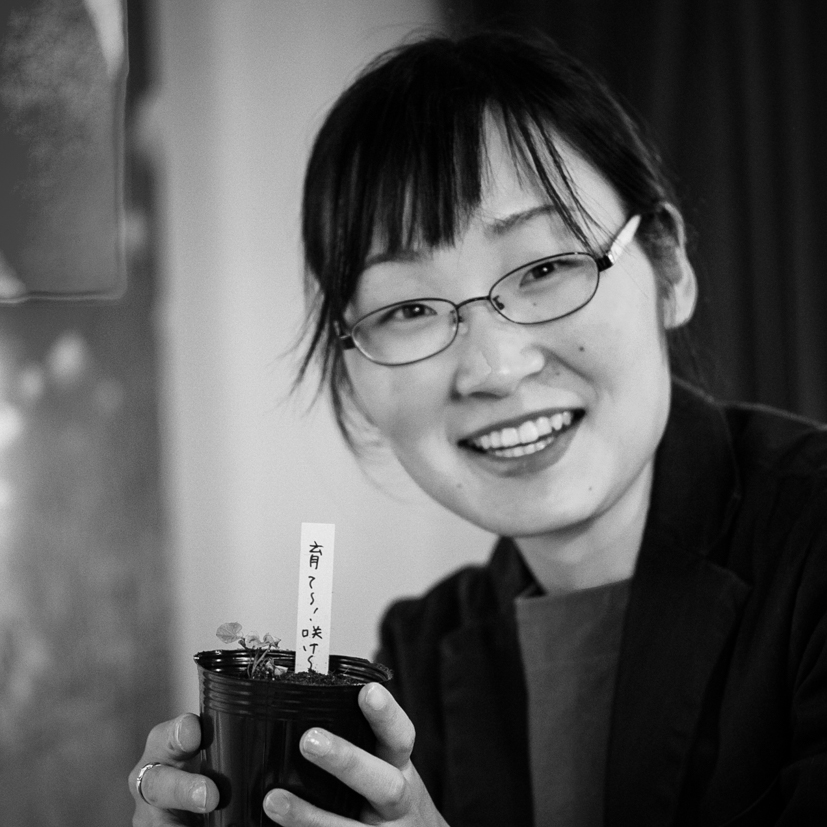3.11の書架 005 『あわいゆくころー陸前高田、震災後を生きる』

『あわいゆくころー陸前高田、震災後を生きる』(瀬尾夏美著、2019年、晶文社)
所感
わたしは3.11SAPPORO SYMPOの実行委員のひとりではあるけれど、他の実行委員のように、支援活動を続けていたり、当事者性を持っていない。そのことについて、時々、「ここにいて大丈夫だろうか」と思ってしまうことがある。
被災地の、同じ場所に通い続けて定点観測しているわけでもないわたしにとって、この本は陸前高田を定点観測する追体験をする助けとなった。
絵や文で表現をするアーティストである著者は、東京から移住をし、数年陸前高田で暮らしながらも、支援者というよりは「生活者」、「旅人」としてあることを自ら選択していた。そうしてまちのひととの対話を丁寧に記録していた。彼女の目と感性を通して綴られる「被災地」にはやわらかさ、人間味、躊躇、が感じられた。
知る権利と、知らないでいる幸せ。知る責任と、知らないふりをする自由。それでも私は知りたいと思う。それはおそらく好奇心のみから生まれるものではない。社会的な私が要請する想像力の拡張への欲求と、誰かのことを想いたいという原始的な欲求。私でない誰かのことを、想いたい。(p.217)
ニュースやひとの話などで断片的には被災地についての情報は得ていたつもりだった。だけど、被災地を歩く経験もその土地土地の方々との関わりも少ないわたしにとっては、どこの、誰の話なのか、結びつけることは難しい。でも、この本を読んで、震災後7年をかけて、陸前高田という土地で、何が起きていたのか、住民の気持ちはどんなであったかを、一部であるけれど知ることができた。
胸に一番ドッと来たのは、波にさらわれた陸前高田の市街地は、山を削って、全面的にかさ上げ工事をして、新しいまちをつくったということだった。かさ上げ工事をしていたことは知っていたはずなのに、全然わかっていなかった。今まで暮らしていたまちの上にまちを作っていたということ。それは大きな大きな「埋葬」のようだと思った。(広島平和記念公園も家々の跡にかさ上げ工事をし、できた公園だとこの本を読んで知った。それもまた「埋葬」のようだ。)
著者は陸前高田ではふたつの喪失があったと記している。まちが波にさらわれたことによるひとつ目の喪失と、そのまちに土が覆いかぶせられることによるふたつ目の喪失。
それは「復興工事」と呼ばれて、あまり住民の民意は反映されてないように思えたし、早さを求められていたのだと思う。でも、その中でも住民は、「新しいショッピングモールの裏の道路の下に家があった」とか「巨石の上に新しい家が建つ」とか、ふたつのまちと生きていることに著者は気付いていた。ひとは、順応していくものなのかもしれない。
誰も止められない多きな構造のなかで、ちぐはぐさを飲み込みながら暮らしを営んでいく。それはきっと、被災地域に限らず、誰しもが抱えている矛盾でもある。悔しさはある。でも、たくましく生きること、したたかに生き延びること、そのこと自体に尊さがある。(p.211)
私事の話になるが、5年程前からわたしが震災から知りたい、と思っていることは「突然の喪失との向き合い方」「故人との向き合い方」だ。そんな個人的なことでいいのかな、という疑問もあったけれど、この本を読んで答え合わせをしたようだった。
人びとが災厄から立ち上がろうとするそのはじまりの時間は、とてもしんどかった一方で、とても創造的でもあったのだ。一つひとつ見返すほどに、あのころ生まれたものたちこそが、誰しもが生涯のうちに直面するなにかしらの困難から立ち上がっていくときに、とても必要なものであると実感されてくる。それは、震災という個別の出来事に関わらない。(p.20)
親しい人たち、まち、財産、景色、時間……などをいっぺんになくした人がたくさんいる。その”さみしさ”は大きすぎて、もっと大人数で分けあわないと抱えきれないじゃないかと思うのです。(p.55)
何とかしてそのさみしさを、一緒に抱えるような勇気を、そのために必要な大きな創造力を持ちたいと思う。(p.71)
私はいま、巨大なさみしさを目撃した。触れ方がわからないから、戸惑いはある。でも、不思議と怖くはないのは、さみしさなら私の中にもあるからだろう。きっと、誰しもの中にもある。(略)私は、”未曾有の災害”で生まれた巨大なさみしさに対して、不思議な親しみのようなものを感じていた。(p.77)
一人ひとりそれぞれの方法で、弔いを続けている。弔うことで、生き残ったその人も何とか生きていく。亡くなった人がその人を支えている。亡くなった人と一緒に生きていく。永遠に続く弔いとは、その人が生きるための術でもある。(p.143)
知っているおじちゃんがテレビに出てきた。私が普段接している底抜けに明るいそのおじちゃんが、亡くなった奥さんを想って、お仏壇に手を合わせて泣いている。おじちゃんの毎日に、そういう時間があったなんて知らなかった。みんなひっそりと喪失に向き合いながら、このまちで生きている。喪失と向き合う、というよりは、付き合うの方が近いかもしれない。見て見ぬ振りをすれば、傷が膿んでしまうかもしれない。真正面から向き合えば、倒れてしまうかもしれない。傷を抱えながら、付き合いながら生きていく。その方法を探りながら、つくりあげながら。(p.218)
自然のむごさとうつくしさに胸を打たれながら、「生活」「暮らし」「死者」に目を向ける著者の文章が、わたしの胸にもシトシトと沁みいるようだった。
自然が豊かで、四季がうつくしくて、どうしようもなく災害の多い国。日本ってきっと、そんな国。ここで生きるとき、どんな風に生きたいだろう?(p.291)
写真:震災後、陸前高田では巨大なベルトコンベアで山から直接砕石を運び、嵩上げを行った。この写真は、そのベルトコンベアの一部(2015年5月)